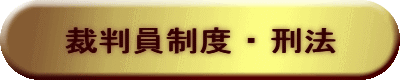
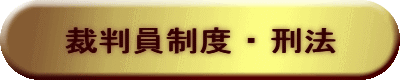
裁判員制度って何?
納税・勤労・教育といった国民の三大義務に付け加えて、人を裁く義務も導入されようとしています。裁判員制度です。
死刑・無期などを含む重大な刑事事件についてのみ、プロの裁判官とともに国民の中から抽選で選ばれた裁判員が、裁判官席について有罪無罪を決し、量刑も決定するという制度です。裁判官の独善を排し、司法の民主化を図ることが目的です。国民の司法参加を憲法上の権利として捉えようという理念には、皆さん方の多くも賛同されると思います。しかし実際に、いざ裁判所への出頭呼出しがかけられれば、仕事や育児介護で参加しづらく、負担を覚える国民も少なくないでしょう。また裁判に参加した場合に課される守秘義務は、どの程度厳しいものになるのかなど、問題も山積みされています。
実施は4年先の2009年頃からと言われていますが、果たしてアメリカの陪審制度のように国民感情にかなう制度として定着し、意義あるものとなるか、注目されています。
司法改革の目玉中の目玉でもあるこの裁判員制度について、司法界はもとより私たち一般国民ももっと関心をもち、論議を深めていくべきだと思います。
刑法が100年ぶりに改正されます!
重大犯罪事件に対する法定刑の罰則強化と、公訴時効期間の延長などを柱とする改正刑法、改正刑事訴訟法が昨年暮の臨時国会で可決成立しました。今年2005年から施行となります。
大学生らのイベントサークルによる集団暴行事件がその一因となって、「集団性的暴行罪」と「集団性的暴行致死傷害罪」が新設され、また一般の性犯罪の厳罰化も実現しました。殺人罪についても、従来死刑または無期もしくは3年以上15年以下の懲役とされていた刑罰を、有期については5年以上20年以下と重くしました。全体的に刑期を長くしたということは、増加する犯罪を抑止し、また被害者の感情にも配慮したものといえます。
刑罰の目的は責任(応報主義)と教育(目的刑主義)の両方があるだけに、犯罪と量刑のバランスをどこに求めるかはなかなか難しいものがあります。
刑法の抜本的改正は、1908年(明治41年)に施行されて以来初めてのことですから、ほぼ1世紀ぶりの見直しです。日本人の平均寿命も驚異的に延び、社会の進歩と共に犯罪も複雑化しただけに見直しは当然だと思います。しかし実際のところ、この改正法によって日本の治安がもっと良くなり、犯罪の防止につながるかは疑問なしとしないという意見もあり、難しいところです。今後の動きにご注目下さい。
戻る
