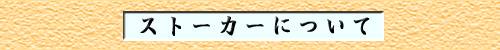
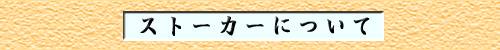
平成9年(1997年)の胡桃通信、「男と女の法律学」では、“ストーカー”について書いています。今では、“ストーカー”という言葉や行為の意味は誰もが知っている事ですが、 平成9年当時には、まだ「ストーカーって何?」という人も多く、この耳慣れないカタカナ言葉を、法律家としていち早く紹介したのが、私のこの「胡桃通信」でした。
ストーカーとは、stalk(=忍び寄る・そっと跡をつける)から発して、好きになった女性や男性につきまとい、相手が嫌がろうがお構いなしに跡をつけて関心を引こうとする、“困った存在”のこと。
概してもてない奴、執念深い奴、思い込みの激しい奴がなりがちで、相手の心情の察しが悪い点で共通 しています。
これが何で法律問題かというと、奴らの行動が犯罪であって犯罪とも言えない、警察に言っても本気でとりあってはくれない、でも鬱陶しくて迷惑千万-誰か何とかしてヨ!と叫びたくなるほど嫌らしい現象で、まぁ人権侵害の一つと捉えるべき、との考えが一般 化してきたことに由来します。
ストーカーの起こす1つ1つの行動は、脅迫罪、器物損壊罪、建造物損害罪や通行妨害罪など、立派な刑事犯罪ですが、これを警察へ届け出ても、いずれも軽微と言えば軽微のため、まぁ今暫く様子を見ましょうという調子で、これまではなかなか真剣には取りあってはくれませんでした。
警察は本来、民事不介入、まして男と女の痴情関係のもつれに警察はいちいち入りませんヨ、という事だったのです。
ところが、平成9年の4月、全国で始めて島根県警が「悪質つきまとい対策班」をスタートさせ、このストーカー被害に対応する動きを示しだしました。
ストーカーが社会問題化し、その度合いを深めるにつれ、殺傷事件に発展するケースも無視し得なくなったからです。この記事の終りには、この「忍び寄る恐怖」には、日本でも、もっと真剣に論議していきたいものです、と私は締めくくっておりました。
あれから3年・・・その間、ストーカー被害は、平成11年(1999年)、8000件を超えました。
そして、平成12年11月24日には、「ストーカー規制法」が遂にスタートしました。
ストーカー行為罪は、被害者の告訴によって罪を問う、いわゆる親告罪です。
つきまとい等については、被害者が警察に届け出れば、まず「警告」を出してもらえます。
それでも繰り返すようなら、本人から聴聞を行い公安委員会が「禁止命令」を出す事になっています。ストーカー被害は、このように警察が動いてくれる事になりました。
もう泣き寝入りする必要はありません。ただ、この法律の対象は恋愛感情等に限定されています。
民事上のトラブルからストーカーに悩まされている人達は保護の外となっています。
とにかく、一人で抱え込まずに弁護士に相談してください。
私たち弁護士は、気楽に相談される立場になって、よりよい方向性を見つけ出すお手伝いをしなくてはならないと思っています。
